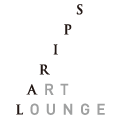作り手の想いを綴るCREATOR’S INTERVIEW。
第4回目は、日常を彩るうつわを制作する
「teto ceramics」さん。
まだ外は肌寒く春訪れを待つ時期に、目黒川沿いのアトリエにてお話を伺いました。
愛着が湧くうつわをつくる
ー“teto ceramics”さんの名前の由来を教えてください。
teto ceramicsさん:基本的には“「手と」一緒に”ということで、ハンドクラフトの「手とceramics(陶器)」を組み合わせた名前にしました。
あとは映画『風の谷のナウシカ』(1984)に登場するキツネリスの「テト」も好きだったのでそれも由来になっています。あの子は、最初は仲良くなるのが難しいけど、仲良くなると心を開いて寄り添ってくれるというキャラクターなんです。
ちなみに僕が陶器を始めた30年ぐらい前、100円ショップが全盛期で、「器が100円で売っているんだったら最高だよね!」と言って安くお皿を買う時代が訪れていました。そんな時代に陶芸を始めたからこそ「とっつきにくいけれども、長く一緒にいると愛着が湧くうつわを」という意味も含めて、この名前にしました。
縁で広がる魅せ方の幅
ー群馬の短大時代は陶芸、東京の大学では舞台芸術を学ばれたとお聞きしました。両方を経たことでどんな影響を受けましたか?
teto ceramicsさん:舞台芸術のコースでは、ジャンルの広い友人がたくさんできましたね。その頃の友人も今では映像関係や雑誌、デザインの仕事をしている人、あとは作家さんになった人もいるし、それはもうすごく良い影響を受けました。短期大学を卒業しただけでは、コミュニティーは小さかったと思います。一回東京に来て進学をしたこと、あとはセレクトショップでお仕事をしたこともあって、「展示やってみない?」 などのお話もいただきました。
そういう経緯もあるので、陶芸作家でありながら、産地ではなく東京で作品をつくり続けてきてよかったな、と。地方で作っていたものとは全然違うアプローチをできているわけで、それは良い経験ができていると思います。
ー縁で魅せ方の幅は変わりますね
そうですね。 産地にも素晴らしい作家さんが多くいますが、東京にいたことでより早くみなさんに知っていただくことができたかなと思います。 もちろん、産地じゃないからこその苦しみもあります。東京でやることが一番だとは思っていなくて、産地でいろいろな知識が得られるのも羨ましいなと。最近は勉強したいなと思って、全国の産地に足を運んでいます。昔も行っていたんですけど、どんどん造詣が深くなるにつれ、作家のもとに足を運んだりとか、あと産地の工場に行ったりとか、そういうのが楽しくなってきていますね。

「民藝品」のような発想で

ー「器」そのものよりも「陶芸品」自体への熱が感じられます。
teto ceramicsさん:「民藝」が大好きなんですよ。自分の作品はポップなカラーリングですが、作り方としては民芸の発想と一緒で、なるべく量産できるように、それ自体がアートにならないように、「たくさん作って、たくさんの方に使ってもらえる作品」を届ける。そうした中で、お客さまが手にとって「この形いいね」「この色がいいね」と言って、ずっと大事に使い続けてくれるものができたらいいなと。「民衆の道具」を作るイメージを持って制作しています。
ー昨年の年末年始にスパイラルで行った展示方法にもその意識を感じました。産地で行うイベントだと、器をたくさん重ねて販売していますが、teto ceramicsさんの器も同じようなディスプレイの方法なんだと驚いたんです。
やはり少なくとも「道具」であることはずっと意識していたいなと思っていて。陶芸の器って「料理を食べるための道具」であって欲しい。飾って満足して、いつまでも使わない器を作りたいとは思ってないので、やっぱり軽かったり、扱いやすかったり、そういったものをずっと意識してデザインしています。
「料理はお腹を満たすもの、手作りの器は心を満たす物」

ー「料理はお腹を満たすもの、手作りの器は心を満たす物」がコンセプトとお聞きしましたが、陶芸を始めた当初からのお考えですか?
teto ceramicsさん:はい、そうですね、器は料理と一体のもの。だけれども、ただ器だけが主役にならないようにしたい。とはいえ、器の立ち位置が「食べて口に入れて味わう」であれば、プラスチックの器でもいいんじゃない?って思ってしまう。でも、そこに陶芸のようなプラスアルファの要素が入れば、心を満たしてくれる部分が生まれると思うんですよね。豊かなテーブルコーディネートになるようにぜひ取り入れて欲しいという気持ちで、こちらのコンセプトにしました。
ー料理は目で楽しむと、より豊かに食事ができる気がしますね
そうですね!プラスチックが悪いわけじゃなく、例えばアジアの方で食べるオレンジとか水色のお皿も可愛いなと思いますよ。ただ、当時は、「目で楽しむこと」など何も考えずに、「お腹に入ればいい」っていう時代になっていたので、シーンで選んで食事を楽しむ時代になって欲しいなと思ったんです。
ー確かに忙しかったりして、「とりあえずお腹だけが満たされればいいや」という気持ちになときもありますけど、食事を楽しむ時間って大切ですよね。
器に盛り付けて友人に振る舞ったり、自分一人でもそうやって食べたり。それって、すごく心を満たしてくれることだなと思っています。
2020年にコロナ禍が訪れて、器がとても注目されたんです。それはお料理をする時間もできたことで、盛り付けを楽しむ人が増えたことが大きいかな、と。それを見た時に、「ああ、心を満たすってこういうことなんだな」と思いましたね。コロナ禍は、悪い部分もたくさんあったけれど、おうちの時間を大切にして家族で食卓を囲む時間ができたり、一人でも盛り付けを楽しみながら食べたりすることができるようになったので、皆さんが食事と向き合う楽しい時間をもらえたんだなと思っています。
「ブルー」と出会い、広がる表現の幅
ーコロナの際に購入したものを、今でも愛用している人も多いのでは?
teto ceramicsさん:たくさんいらっしゃいました。 スパイラルで展示した2022年は、NEWカラーとしてピンクシリーズを出したんです。その際、ブルーに続いて買い足しに来ました、という方がいらっしゃいました。それで、自分の中では、コロナ禍の出来事は、器にとっては良いタイミングだったんだと思いましたね。
ー先ほどスパイラルで初めてピンクのカラーを出したおっしゃいましたが、今までどのようなカラーを取り扱ってきて、その色に対してどんなこだわりがありましたか?
実は元々艶のある白と、マットの白しか作っていなかったんです。その後、黒や茶色を出して、ブルーの器も取り入れてみました。最初は、こういうポップなカラーの器ってどうなの?と思っていたのですが、作ってみたらとても良いものに仕上がりました。
食べ物を器にのせると必ず立体的になるし、盛り付けも上手にできるので、とても良い色だなと思いましたね。ブルーと出会ったことで、自分の表現の幅が広がった感じがしました。
ちなみに、スパイラルで出したこの新作は、もともと同じ色の釉薬なんです。ですがそれぞれ窯の中で窯変といって化学反応が起きているんですね。では何が違うかと言うと土が違うんです。土が違うことで、この釉薬に起きる化学反応が違って、こっちは白になるんですけど、こっちは土の反応で緑に出るんですね。今後はこういった違いを利用して色々表現できたらと思ってます。

いろいろな分野の人と交流する

ー日常生活の中で、例えば趣味や人間関係、あるいは他の作家さん、料理家さんなどから作品づくりに影響を受けることはありますか?
teto ceramicsさん:実は「これ作ってよ」と言われて作った時の方が良いものができたりするんですよ。 自分の世界観って意外と狭いので、ある程度同じ発想のものしかできないんですけど、料理人やギャラリーの方が欲しいものって、自分とは全く異なる目線を持った方たちのアイデアなので、作ってみると自分の世界から一歩広がった素敵なものが生まれます。だから、積極的に色々な分野の方々と交流持つことにしています。
写真もそうですね。広報用の写真をギャラリーさんが撮影してくださったときや、お客さまがインスタグラムで投稿してくれたものを見ると、また違った印象で素敵に見えるので、すごく大事に思っています。みなさんが撮影してくれた投稿。あれこそ宝物です。
ー陶芸教室を開いているとお聞きしましたが、いらっしゃる方の共通点があったら教えてください。
みなさんやっぱりお料理が好きですね。あとコーヒー好きの方も多い。結構こだわりがあって直接鼻に香るような角度にしたいというリクエストもあります。 あとは手に持った感覚を大事にされる方が多いですね。器を手に持って食べるのって日本特有なんですよ。海外だとスプーンを使いますが、日本は違うので、そういった口当たりとか手触りとか、みなさんこだわっている印象です。

愛おしく思えるような雰囲気を目指したい
ーご自身の制作の中で大切にしていることやこだわりはありますか?
teto ceramicsさん:特別なものを作っているという意識を持たないようにしています。上手になっていくと面白くなくなっちゃうんですよね。だから、「なんなんだ。いつまでもこういうところが詰めが甘いな」が個性だと思います。そこが愛着を持てる部分だと思うので、下手な部分を愛してもらえるように、そこを上手に表現できるように、愛嬌のある作家でいたいな、と。 いつまでも「子供が描く一風変わった絵」のような、愛おしい雰囲気を目指せるように頑張りたいなと思っています。
ーいつも同じものが作れるとしたら、それこそ人間じゃなくてもいいですよね。
ここから先はそういう時代ですよね。技術が発達していくので、そういったものは技術の方でカバーしてもらって。人間味とか人間臭さとか、クスッと笑えるような、そういったあたたかいアプローチのできる「作家」として、今後もいられたら嬉しいなと思いますね。それが今後の目標です。
Hike!Hike!への想い
ー開催中のHike!Hike!への想いをお聞かせください。
teto ceramicsさん:“Hike”はハイキングをするという意味。山に出かけるように、楽しい気持ちでイベントに参加してもらいたいという思いを込めて、Hike!Hike!という名前で開催しています。
春から新緑の季節。生きている世界や生活がどんどん色鮮やかになっていく中で、みなさんに、「外に出て楽しみましょう!」「新しい明るいものを取り入れて、面白い生活を過ごしましょう!」という、前向きな意味を込めたイベントです。
ー実際私も昨年の5月にイベントを見て、当時の展示風景が目に焼き付いています。4月の慌ただしさが落ち着いて、慣れてきたけど少し不安な気持ちがあったんですが。 この展示を見て、気分が明るくなりましたね。
teto ceramicsさん:4月から5月になるときって気持ちが落ち込んでしまう方も多い時期ですよね。ただ季節の面ではどんどん明るくなっていくので、そんな方の新しい刺激になるような、目で見て「わぁ!」って明るい気持ちになるような、お客さまの心に火をつけて、楽しい空間を作りたいと思っています。
ー参加される作家さんはteto ceramicsさんがお声がけしてらっしゃるのですね。
楽しい気分になるような、ひとつ自分に新しい世界観が広がるようなブランドを意識して選んでいます。
僕は、お料理の時にひとつ雰囲気を添えられるようにしているんですよ。 「生活にプラスワンの楽しみを。」といった意味で、まっしろなテーブルやお皿だけではなく、この一品で気持ちが上がるようにしたいんです。 Hile!Hike!も同じで、例えば、東京に転居されて生活も落ち着いた頃に、ひとつまた新しいものを見つけに、街を散策していたとき、スパイラルという場所を知り、その方に寄り添えるようなイベントにしたいな、と。お洋服屋さんと、靴屋さん、バッグブランド、そして僕の器、面白い4ブランドでお待ちしています。新しい生活にひとつ色を加えていただけたらと思っています。

ーteto ceramicsさんのお人柄は周りの士気を上げる明るさを持ち合わせていらっしゃいますよね。
たぶん器よりも、自分が一番Hike!Hike!じゃないかなと。笑
ーーー・ーーー・ーーー・ーーー・ーーー・ーーー・ーーー・
Hike! Hike!
会期:2025.4.24(thu) -4.30(wed) 11:00-19:00
会場:Showcase(Spiral 1F)